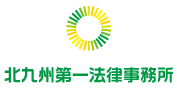財産開示手続等について

はじめに
例えば、相手にお金を貸したけれども、約束の期限になっても返してもらえないというような場合、裁判所に訴えを提起して支払いを命じる判決を取得し、その判決に基づいて強制執行の手続を行うことができます。
しかし、金銭債権について強制執行の申立てをするには差押えの対象となる財産を特定する必要がありますので、相手(債務者)にどのような財産があるのかが分からないと、強制執行を行うことは困難です。
そこで、民事執行法では、債務者の財産状況の調査に関する制度として、財産開示手続と、第三者からの情報取得手続を定めています。
財産開示手続について
財産開示手続は、裁判所が債務者を呼び出して、その財産について陳述させるという手続です。
財産開示手続は、平成15年の法改正により創設されました。しかし、債務者が開示期日に出頭しなかったり、虚偽の陳述をしたりしても、30万円以下の過料という弱い制裁しかなかったため、実効性が十分ではなく、利用件数は多くありませんでした。そこで、令和元年の法改正により、手続違反に対する罰則を、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金と強化されています。
この手続きの申立てをすることができるのは、金銭債権についての判決等を有する債権者などです。
第三者からの情報取得手続について
第三者からの情報取得手続は、令和元年の法改正で新設された制度で、裁判所が公的機関や金融機関等に、債務者の財産に関する情報を提供させるという手続です。
具体的には、①登記所から不動産に関する情報を取得する手続、②市町村や日本年金機構等から給与債権(勤務先)に関する情報を取得する手続、③金融機関等から預貯金債権等に関する情報を取得する手続があります。
これらの手続の申立てをすることができるのは、①不動産に関する手続と③預貯金債権等に関する手続については、金銭債権についての判決等を有する債権者などです。また、②給与債権(勤務先)に関する手続については、扶養義務等(養育費など)の金銭債権または人の生命身体侵害による損害賠償請求権についての判決等を有する債権者です。
おわりに
このように、近年の法改正によって債務者の財産状況の調査に関する制度が強化され、これらの手続きによって債務者の財産が分かった場合、その財産を対象にして強制執行をすることができるようになりました。
相手が支払いをしてくれないということなどでお困りの場合は、一度、弁護士にご相談下さい。
ご相談予約はこちら▼
電話:093-571-4688