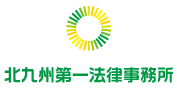婚姻費用が支払われない時、どうする?〜交渉・調停・強制執行までを解説
 夫婦は互いに相手方に自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)があります。
夫婦は互いに相手方に自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務(生活保持義務)があります。
そこで、別居した場合や、同居中でも相手方が生活費を渡してくれないときには、収入が少ない方は、相手方に対して婚姻費用の支払いを求めることが出来ます(民法760条)。
相手方に請求しても婚姻費用を支払ってくれない場合はどうしたらよいでしょうか。
1 交渉
弁護士の代理で相手方に請求する方法があります。相手方が、弁護士の請求であれば応じる場合もあるからです。
もっとも、この場合に婚姻費用の支払いの合意書を作成しても、未払いの場合に給与差押えなどの強制執行ができません。そこで、強制執行に備えて公証人役場で執行受託文言付きの公正証書を作成しておく必要があります。
2 調停
相手方が婚姻費用を支払ってくれない場合には、裁判所で話し合いをすることもできます。
これが婚姻費用分担調停の手続きです。申立は当事者でも出来ますし、弁護士に代理人になってもらうこともできます。申立書は裁判所のホームページに書式がありますし、裁判所で申立書の書式を貰うこともできます。
弁護士が代理人になった場合には、婚姻費用分担調停の場合には当事者が欠席でも期日は進められますが、期日が充実するように、できれば当事者の方も出頭して貰った方がよいと思います。
調停期日には、相手方と別の待合室で待っていて、各々調停室に入って主張を調停委員に伝えます。
調停の場合は裁判所が合意内容について調停調書を作成してくれるため、未払いの場合には調停調書を元に強制執行をすることができます。
そこで、当事者(ないし代理人)において、合意内容を別途公正証書などの形で書面化する必要はありません。
3 審判
仮に婚姻費用について金額や支払い方法等折り合いがつかなければ、調停を不成立となりますが、この場合特に何もしなければ自動的に審判に移行します。
調停手続きでも、当事者の要望や主張の話し合い折衝は続いていますが、当事者の話し合いがつかなくても、最終的に裁判所が提出された資料等に基づいて婚姻費用の分担の有無や金額、支払い方法等を決めます。
主張や証拠が出尽したら、裁判所は審理を終結して、裁判所が審判書を作成し、審判が出ます。
双方は不服申立手続きをすることができますが、双方とも不服申立をせずに審判が確定したら、相手方が支払いをしてくれないときには審判書を元に強制執行をすることが出来ます。
4 離婚裁判との関係
(1)申立時期及び手続き
ア 離婚裁判をしながらでも、離婚するまで婚姻費用の支払いを求めることが出来ます。
そこで、離婚調停の申立と共に婚姻費用の分担調停の申立をあわせて行い、調停期日を同じ日に実施して、両方について話し合いを進めていくこともできます。
ちなみに、裁判所の書式では、離婚調停の申立書の表題が「夫婦関係調整調停(離婚)」で、婚姻費用分担調停の申立書の表題が「夫婦関係調整調停(円満)」です。両方を同時申立するのは一見矛盾しているようにみえますが、婚姻費用は婚姻中であることが前提ですから、問題はありません。
イ 婚姻費用分担額は、双方の収入額資料がそろえば特別教育費などがなければ支払額をすぐに算出できます。
そこで、婚姻費用の分担調停を先行成立させて、婚姻費用の支払いを受けながら、離婚調停期日を重ねていくこともよくあります。
(2)未払い婚姻費用の処理
離婚調停で和解する際の未払婚姻費用の処理方法は、下記の二つがあります。
①和解書の中で、未払婚姻費用の給付条項を別途設ける。
②和解書の中の、財産分与の項目の中で清算する。
5 以上の諸手続きによって、婚姻費用の支払いの合意が出来たにもかかわらず、支払いが滞った場合には、裁判所に給与差押えや預金差押えの強制執行をすることになります。
差押え対象が給与であれば、勤務先が判明していないとできませんし、転職してしまえば、転職先の給与を改めて差押えすることが必要です。
6 未払い婚姻費用の請求をお考えの方は、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
ご相談予約はこちら▼
電話:093-571-4688