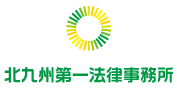固有財産である不動産からの家賃収入と財産分与について
 夫婦の一方に、相続財産である不動産からの家賃収入があり、それを原資とする預金等の資産が形成されている場合に、離婚時の財産分与におけるそれらの預金等の資産の処理が問題となります。
夫婦の一方に、相続財産である不動産からの家賃収入があり、それを原資とする預金等の資産が形成されている場合に、離婚時の財産分与におけるそれらの預金等の資産の処理が問題となります。
1 財産分与対象性について
(1)不動産自体
夫婦の一方が不動産を所有していても、それが相続により取得した相続財産である場合には、夫婦が協力して形成した資産ではないので、そのような不動産は、特段の事情がない限り、いわゆる固有財産として財産分与の対象外とされます。
(2)家賃
ア また、上記不動産からの家賃収入は、固有財産からの果実として、財産分与の対象外とも考えられます。
しかし、賃料は、時の経過だけによって預金元金から生み出される預金利息とは性質が異なります。つまり、賃料は賃貸不動産の維持・管理という人の努力や工夫が加わることで初めて生み出されるものですから、特有財産である不動産から発生した果実であっても、一律夫婦の実質共有財産から除外される性質のものではなく、賃貸不動産の維持・管理ひいては回収された賃料総額に対する寄与割合が問題となりえます。
そこで、家賃収入を得ることについて夫婦の他方による寄与がある場合には、家賃収入を原資とした資産に対する寄与割合を考慮する必要があります。
2 家賃収入への寄与分割合の考え方
では、仮に家賃収入への一定の寄与が認められた場合に、具体的な寄与割合はどのように考えるべきでしょうか。
ある事件では、夫婦の他方が、仲介業者をほぼ入れずに、契約書作成、保守管理、賃借人対応、トラブル対処、振込以外の賃料受領、延滞賃料督促、退去時清掃等賃貸物件管理一般を担当していました。物件は古く、戦前建築の物件さえあり、継続的な賃料収入をえるためにも保守管理は不可欠であるところ、小修繕については業者を手配せずに自分で行っていました。
この事件については、後述するような不動産収入にかかる経費の考え方をもとに、他方配偶者の賃料収入への寄与割合を3割とすべき旨を主張・立証しました(「<当方の寄与割合についての考え方の主張>」)。
これに対して、裁判所は、「本件記録からうかがわれる関与の内容および程度、申立人の特有財産からの果実であることなどからすると」と理由を述べた上で、基準時において存在する賃料に関する財産のうち3割を夫婦の実質共有財産とみとめ、結局さらにその半額が分与されることになりました。
個別事例にすぎませんが、同種事案検討の際の参考になると思われるのでご紹介しました。
<当方の寄与割合についての考え方の主張>
(1)経費の考え方
ア 不動産業者ヒアリング結果
遠隔地の家主から丸投げ管理を受託している、知り合いの不動産業者二社から当方が聴取した内容を主張しました。
不動産業者いわく、基本業務は集金代行だけであり、その場合の業務受託料は8~15%と2年に1回の契約更新料家賃1月分であること、不具合修理は連絡に係わる程度で業者に紹介料をもらって紹介するだけであること、家賃の3割をもらっても当方が担当していた維持管理業務は断るとのことでした。
イ 国税庁の消費税課税時の経費
国税庁の消費税課税時の簡易課税制度によれば、不動産業の場合の売上高に対するみなし仕入れ(経費)は40%とされていること、今は消費税法だけで使用されているものの、国税庁の膨大な量と長井実績から算出された数字であり、業種別利益率を見る場合の一つの指標として常識的に使われているものであり、本件でも参考にされるべきであることを主張・立証しました。
ウ 実際の経費
実際の経費については、相手方から提出された、直近確定申告書の収支内訳書(不動産所得用)に基づき、実際の収入金額のうち約20%が経費である旨主張・立証しました。
(2)本件寄与割合について
そこで、上記の消費税の簡易課税制度を参考に不動産業の家賃総額の40%を経費として計算し、残り60%を利益として、さらにその半分である30%を当方の寄与割合とするのが相当である旨主張しました。
しかも、当方負担の維持管理業務は通常の不動産業者の丸投げ物件の管理業務より相当負担が重いこと、また実際の経費20%に10%程度上乗せしたにすぎないことを考慮すると、30%の寄与割合は過小ではあっても過大とはいえないことも当方の主張が相当であることを裏付ける根拠として主張しました。
以上